日本で株式投資を行っていると、年末に向けて気になるのが「損益通算」と「最終取引日」です。
特に税務対策をしっかりと考えなければ、知らず知らずのうちに税金を払い過ぎてしまうことがあります。
この記事では、損益通算の仕組みと最終取引日の重要性について解説します。
損益通算とは?
損益通算とは、株式などの投資による利益と損失を相殺して税金を計算する仕組みです。
具体的には、ある年に株式投資で得た利益がある場合、その利益に対して税金が課税されます。
しかし、同年に株式投資で損失が出ている場合、その損失を利益から差し引いて、課税対象となる利益を減らすことができます。
これによって、税金を軽減できる可能性があります。
損益通算の対象となるのは、以下の3つの種類の所得です。
- 株式譲渡益(株式の売却益)
- 配当所得(株式から得た配当)
- FXや先物取引などの利益
これらの利益と損失を通算することができますが、国内株式に関しては、株式譲渡益と配当所得が主な対象となります。

損益通算の具体例
例えば、2024年にA株を100万円で購入し、120万円で売却して利益が20万円出たとします。
一方で、B株を80万円で購入し、60万円で売却して損失が20万円出た場合、損益通算を使うと、A株の利益(20万円)とB株の損失(20万円)が相殺され、結果的に課税対象となる利益は0円となります。
このように、損益通算を利用することで、税金を支払わずに済む場合があります。
ただし、注意が必要なのは、損益通算の適用は同一年内の取引に限られるという点です。
そのため、年を跨いで損益通算を行うことはできません。
最終取引日と受渡日
株式投資を行っている場合、年末に向けて注意したいのが最終取引日です。
最終取引日とは、税務上、課税対象となる株式売買が反映される取引日ですが、実際には受渡日が基準となります。
受渡日とは、株式の売買代金が実際に決済される日で、一般的に取引成立日の2営業日後にあたります。
この受渡日が基準となるため、取引が成立した日(注文を出した日)が年内であっても、受渡日が翌年にずれ込む場合、その損益は翌年の課税対象となります。
2024年に関しては、最終取引日が12月26日(木)となります。この日までに取引を終了する必要があります。
つまり、年末に損益通算を行いたい場合、年内に売買を決済し、その受渡日も年内に収める必要があるということです。

損益通算の活用方法
年末に損益通算を最大限活用するためには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
- 年内に損失を確定させる: 損益通算を行うためには、年内に損失を確定させることが必要です。これには、年内に損失を抱えた株式を売却して、その損失を利益と相殺する方法があります。最終取引日までに損失を出しておくことを考慮しましょう。
- 受渡日を確認する: 年内に取引を行っても、受渡日が年を跨ぐ場合、その損益は翌年に反映されます。年内に損益通算を行いたい場合は、受渡日が年内であることを確認しておくことが必須です。
- 配当所得の取り扱い: 配当金も損益通算の対象ですが、配当金の支払い日が年をまたいでしまうと、翌年の課税対象となるため、支払われるタイミングを確認しておくことが重要です。
- 損失の繰越: 年内に損益通算を行っても、損失が利益と相殺しきれなかった場合、翌年以降に繰越して利益と相殺することができます。この繰越は最長3年間可能です。
最後に
損益通算を賢く活用することで、株式投資による利益にかかる税金を減らすことができます。
しかし、そのためには受渡日が基準となる点を十分に理解し、年内に損失を確定させて税務上の取り決めを整理しておくことが欠かせません。
特に年末は、税金対策を考えた取引を行う絶好のタイミングです。余裕を持って計画を立て、賢く税務を乗り越えましょう。
この記事では、損益通算や最終取引日、受渡日が基準であることについて詳しく解説しました。
税務に不安がある場合は、専門家(税理士)に相談することもおすすめします。
年内に株式の損益はスッキリさせて良い新年を迎えましょう!
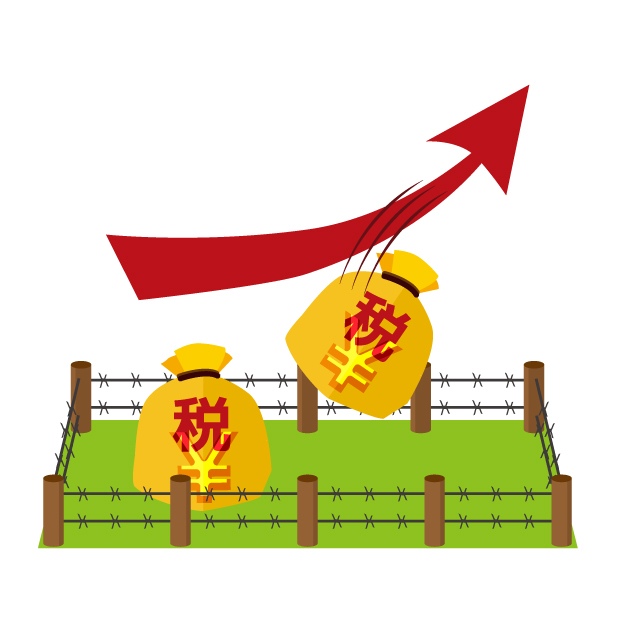


コメント